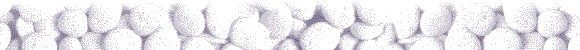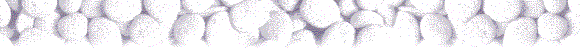
 色々な石の色
色々な石の色
実は根本的な所で深い関わりがあります。
美しい色を持つ石は、時に絵の具の原料となり、
また、時には、その石の名が色の名前としても、流通してきました。
鉱物類が絵の具の材料に使われた理由は、
色合いがその鉱物でしか出せず、他のものでは代用出来ないこと、
(ただし、現在では人工的に作られることも可能)
それから、鉱物によって作られる色は、安定していて、
長時間光に当たっていても、色あせないことです。
この2つの理由で、鉱物からは、多くの絵の具と、様々な色名が登場し、
それによって、数々の名画が誕生しました。
…ということで、「石が素になっている色」とは、どういう色なんでしょう!?
ここでは、そのいくつかを簡単に紹介してみます。
(説明は、左→右の順で説明していきます)
まずは、青系統から…
サファイア・ブルー(下図左側)、ラピスラズリ(下図中央)、
それと、アメシスト(下図右側)。



ペルシャの神話では、世界の基盤はサファイアで出来ていて、
空はその色を映して青い、と、言われていました。
空の色や、目の色を表現する時に、使われます。
ラピスラズリは、海を越えて伝わった、という意味で、別名「ウルトラマリン」。
和名では、瑠璃色、群青色とも呼ばれ、群青というのは、
「青が群れ集まる」という意味があります。
アメシスト、和名は紫水晶で、名前の通りの濃い紫色を指します。
石自体は、紫が濃いものから薄いものまで様々ですが、
やはり、上記の色のように、紫が濃い方が、価値は高くなるようです。
次に、赤系統です。
ガーネット(下図左)、アゲイト(下図中央)、ルビー(下図右)。



ガーネットには、多くの種類があり、色も様々ですが、
色名として使われるのは、紫がかった、濃い赤い石です。
アゲイトとは、瑪瑙のことですが、色名として使われるのは、
赤縞瑪瑙(サードオニックス)の色。
石自体は、縞模様なので、色が特定出来ませんが、
この石を砕いて絵の具にすると、こういう色になるとのこと。
ルビーは、石の名も色の名も、よく知られていますよね?
血や唇の例えにも、使われますが、この色の歴史は古く、
16世紀ごろから、すでに使われていました。
青、赤…と来たら、次は緑でしょう!(根拠なし)
マラカイト・グリーン(下図左側)、ジェード・グリーン(下図中央)、
それからエメラルド・グリーン(下図右側)。



マラカイトは、和名「孔雀石」。
石の通りの緑青に近い、濃い緑色を、マラカイト・グリーンといい、
古代、クレオパトラが、アイシャドウに使っていた
とも言われています。
ジェードは翡翠のこと。(正確な石名はジェーダイトですが)
翡翠の明るい緑色を、ジェード・グリーンといいます。
実は、翡翠を宝飾品として使ったのは、日本が最初と言われ、
古墳からも、翡翠の製品が出土しています。
エメラルド・グリーンは、とても有名ですよね?
絵の具の色名として用いられ、多くの画家達に愛用されています。
ゴッホは、「糸杉のある麦畑」で、 糸杉を、
ビリジアンとエメラルド・グリーンとウルトラマリンで描きました。
緑系統は、もう少し続きます。
ターコイズ(下図左)、アクアマリン(下図中央)、
オパール・グリーン(下図右)。



ターコイズは、トルコ石の、青緑色に由来します。
青と緑の間を指す、代表的な色ですが、それ故に、この色は
「ターコイズブルー」「ターコイズグリーン」という、両方の形容が存在します。
アクアマリンは、石自体「アクア(水)マリン(海)」の名の通り、
水色が代表的ですが、色名になると、
何故か上記のような青緑色を指します。
オパールは、遊色といって、色が光の加減で虹のように見え、
一定しませんが、その色合いをまとめたような
薄い黄緑っぽい、乳白色の色を、オパール・グリーンといいます。
えーと、当然これだけってことはないのですが、
とりあえずここまでにしておきます。
え?色が似ていて、余り区別出来ない!?
…ごめんなさい。私の色作成の技術は、これが限界だったんです。
でも、これを見たきっかけに、名画の鑑賞なんぞしてみると、
ちょっと違った見方が出来るかもしれませんよ!!
ただし、一歩間違えると、「理屈っぽい人」になる可能性大!
| その他雑談 | トップ |