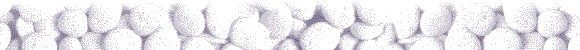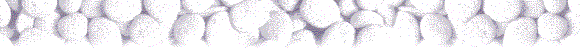
 削って分かる本当の色
削って分かる本当の色
「事典などで思わず見なかったことにしちゃう」
と書きましたが、同じような扱いになるのが「条痕」の所。
「じょうこん」と読みますが、これも
よく知らないと「ふぅ〜ん」で終わる項目だったりします。
一応調べておこう…と見てみると
「素焼きの陶板に擦り付けた時の色」などと
書いてあって、ますます「ふぅ〜〜〜〜ん(-_-)」って感じ。
「だからそれが何!?それって鉱物を分類する上で必要なワケ????」
と、事典の筆者に心の中でつっこんだりして。
まぁ、それは全て私の実体験だったりしますが…(^^;)
確かに「素焼きの陶板に擦り付けた時の色」などと
書いてあると、何のことかさっぱり分かりませんが、
こう書くと分かり易いかもしれません。
「その石が粉になったら何色なのか?」
そう、条痕とは、鉱物を磨り潰した際の色を
書いてある項目だったのです。
「ええ?石って、粉になったら色が変わったりするの?」
…変わるんですよ。それが。
しかも、時折思いがけない色が表れたりします。
例えばアメシスト。
アメシストといえば和名「紫水晶」の名の通り
美しい紫が特徴的ですが、この石を粉にしたら
あの紫はいつの間にか消えてしまい、
気が付くと、無色になってしまいます。
何故なら、紫水晶の紫は、
元々無色の水晶に、酸化鉄などが混じって出来た色。
不純物がある程度の量あるから紫に「見える」だけなので、
細かくすればする程、その量は減り、
粉になったら、もう紫に見えるだけの量はありません。
だからいつの間にか無色になってしまうのです。
このパターンを「他人の色=他色」と言い、条痕は「白」。
「他人の色」があるなら「自分の色」だって、当然あります。
例えば孔雀石。これもキレイな緑色ですが、
この色の元は銅。孔雀石の主成分は銅なので
この場合、擦ろうが、粉にしようが、緑色はしっかりと残ります。
これが「自分の色=自色」で、条痕はもちろん「緑」。
これで「条痕」の項目もきちんと読み取れるようになりますね!?
条痕も、よく読むと結構面白いです。次のポイントは「思いがけない色」。
例えば赤鉄鉱の場合。

形はいろいろありますが、色はどの石を見ても大抵こんな感じで
「何で“赤”鉄鉱なんだ?黒鉄鉱とかの方が合ってるのでは?」
と、つい疑問に思ってしまいますが、これも条痕に注目すると、謎が解けます。
赤鉄鉱の条痕は赤。そう、この石、集まってると黒っぽいですが
細かく粉にすると、真っ赤になる石だったのです。
その赤色は、他の鉱物内に入った時に、しっかり発揮されます。

上の石は、赤水晶。水晶の中に赤鉄鉱が入った為の赤色です。
赤いジャスパーの赤も、同じ赤鉄鉱。
これで、「赤鉄鉱」の“赤”の理由が分かりましたね?
ちなみに、条痕の調査ですが、当然、条痕板より柔らかい石でないと、
そもそも粉にならないので、調査出来ません。
具体的には硬さ5〜6くらいまで。
7以上になると、ちょっと厳しいようです。
(だからアメシストの条痕はあくまで憶測ですね)
ただ、硬さが7以上というと、石英系(紅水晶、紫水晶etc)、
ベリル系(エメラルドやアクアマリンetc)、
コランダム系(ルビー、サファイア)など、測るまでもなく、
当然条痕は白いんだろうなぁ〜という石ばかりなので、特に問題ないようです。
それから、これは私の感覚ですが、「ガラス光沢系」の石は
「無色+α」の他色が多いので、条痕は、おそらく白ばかりになるのでは?
むしろ、条痕が重要になるのは、「金属光沢系の石」ですね。
こういう石のデータを見る時は、「条痕」の項目、重要ですよ!
| 鉱物豆知識 | トップ |